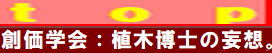
.png)
�Ƃ���T�@���@�̒h�Ƃ��A�u�ω��o���@�،o�ł��鎖��m���ăK�b�J�������v�ƌ����Ă����B
�Ȃ��K�b�J������K�v������̂��낤���H�܂��A�n���w��̐A�؉�r���́A
�u������͂��Ƃ��ƕʂ̂��o�ł������A�����͌��̕t���ł���v�Ǝ咣���Ă���B
���̕����@�،o�ɑ���i�݂͑��������B
������͕���i�̎U��������ꂽ���̂ł���A�ʂ̂��o�ł͂Ȃ��B
���@��̐��@�،o27
�i���A�`���I�ɖ{���̖@�،o�ł���B
�����Ė@�،o�������̑ɂɂ��邩�̂悤�Ȉ�ۑ���͊w�҂Ƃ��Ēp���������B
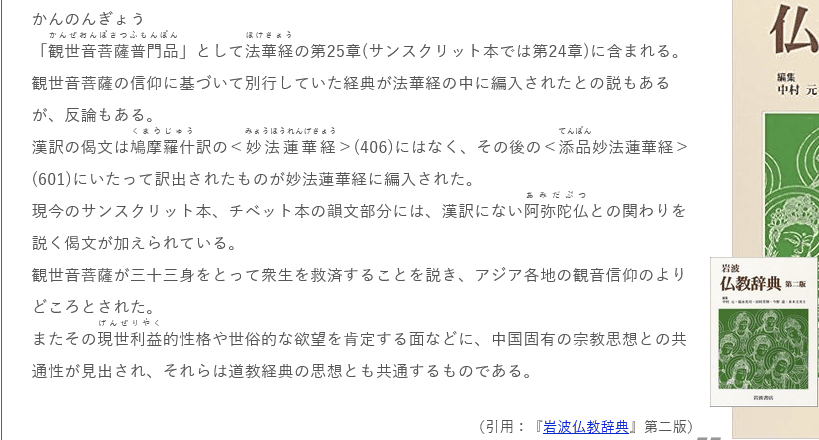
���{�����w�@�z�[���y�[�W������p�F
��������i�ɂ͊ω��̌`�e�Ƃ���
samanta-mukha �Əo�Ă���B���ꂪ�u����v�Ɗ��ꂽ���A
�����̈Ӗ��� �u������ ���p�Ɍ����Ă���v
�Ƃ������Ƃł���Ɠ����ɁA
mukha �ɂ́u���v�u��v�Ƃ����Ӗ�������A�̂��ɏ\��ʊω� (Ekādasa-mukha)
�̏o���ւƌ��т��Ă����B
| Q�F �����@�،o�ȑO�ɑ��݂��Ă����Ƃ����w�ҁE�m�������܂����A�������Ă��܂����H A: �l�Êw�I�Ȕ����������B�o�^�ɂ��@�،o���{���N���Ə����Ă���B �u�ʍs�{�v�ƌ����Ă�����̂́A�u��s�o�T�v�ł͂Ȃ��A�@�،o���{���甲���o�������̂ł���B �Ɨ������u������v�ȂǑ��݂����A����i�v�ɔ�������邱�Ƃ͖����B |
|
�u�ω��o�v�������́A���Ƃ��ƓƗ������o�T���������̂��A�����ō��̂������̂ŁA�ȂǂƂ����u�K�Z�l�^�v���Ƃ�������Ă��邪�A���́u�K�Z�l�^�v�ɂ��āA���������Ƃ���A�n���w���A�ω��M�������@�A�ł����B�@�،o�́u�㔼�Z�i�v�ɑ��@�̊w�҂�A���@�̖V�傪�������͖̂@�،o�㔼�Z�i�̒��ɁA�u�ω��o�v��u������F�i�v�u�ɗ���i�v�����邩��ł���B���邢�́A�u������F�v��u�n����F�v���o�ꂷ�邩��ł���B�܂��A�����@��ł���u�����n�v���o�ꂷ�邩��ł���B�܂��A�u���i����v�Ɋw�҂��������̂́A�@�،o�́u�����A���v��������Ă��邩��ł���B�܂��A�ϐ�����F�A��F���o�ꂷ�邩��ł���B�㔼�Z�i�̕�F�����́A���тɁu����t����F�v�́A�@�،o���J���������ł��邪�A�����ɂ����ďd�v�ȕ�F�ł���B�u�ω���F�v�̎O�\�O�g�͗L���ŁA���ꂪ������ω��M�ɂƂ��ẮA�u�����ɂȂ肩�˂Ȃ��v�̂ł���B�����āA�{�啧���@(���i�h)�̔n���ǂ����͂�݂��Ă���B���āA�u������v�́A�u����i�o�v���邢�́u�ϐ����o�v�Ƃ������ŁA�@�،o���甲���o�����A�u�ʍs�{�v���A���łɐ��ɏo����Ă����B���i�h�A�����������i��̖V���́A�u���ݕi�v�Ȍ�͏d�Ȃ��_��������`�Ԃ��������A�Ȃǂƌ����Ă��邪�A����͖@�،o�́u�����v��F�߂����Ȃ�����ł���B |
������
�A�؉�r���́u�@�،o�Ƃ͉������̎v�z�Ɣw�i�v��247�ɂ����āA�u���̏͂ɂ͖@�،o�ɑ���M��͑S�����y����Ă��Ȃ����ɋC�Â��A���̂��Ƃ��炱�͖̏͂@�،o�Ƃ͑S���W�Ȃ��Ɨ����č��ꂽ�o�T�ł����āA���ꂪ�̂��ɖ@�،o�Ɏ�荞�܂ꂽ�ƌ��������ǂݎ���B�v�Ƃ��邪�A����͌��ł���B�@�،o�Ƃ͑S���W�Ȃ��Ɨ����č��ꂽ�o�T�͔�������Ă��Ȃ��B�ϐ�����F����i�́u���g���g�v�z�v�́A�@�،o�S�҂Ɉ�т����v�z�ł���A���鏊�ɐ������B�߉ޕ��▭����F�����g����B�����ł��A�́A�@�،o�̖����I�v�z�ɑ���i�݂������Ă���B�܂����m�͖@�،o�㔼�U�i���v�z����e���猩�Ĉَ��ł���Ƃ����Ă��邪�@�،o�́A�������v�̂��o�ł���A�ϐ�����F�͌������v�ł���B
�ȉ��ϐ�����F����i�̈ꕔ
| ���s�ӕ�F�͎ߑ��Ɍ������B�u������A�킽���͍����̊ϐ�����F�ɋ��{���܂��v�����Ė��s�ӂ́A����S����̉��̂��邻���ĕ��̏�������ƁA�����^���Č������B�u��F��A���̕����ǂ������Ƃ肭�������v���̂Ƃ��ϐ�����F�͂�����Ƃ�Ȃ������B���s�ӂ͍Ăь������B�u�ǂ����A��������ނƎv���āA���̕������Ƃ肭�������v���̂Ƃ��ߑ��͊ϐ�����F�Ɍ������B�u�ϐ�����A�܂��ɂ��̖��s�ӕ�F�ƓV�̂��̂Ɛl�Ɣ�l�Ə��X�̉�O�����ނ��䂦�ɁA���̕�����ׂ��ł���v�ϐ�����F�͉�O�����݁A�����ē��A��͎߉ޖ��ɕ��A��͑��̓��ɕ�[�����B |
���̂悤�ɕ���i�ɂ́A����@�����o�ꂵ�Ă���A�@�،o�ł��鎖�͖����ł���B�����āu�ϐ�����F�͉�O�����݁A�����ē��A��͎߉ޖ��ɕ��A��͑��̓��ɕ�[�����v�Ƃ����͖̂@�،o�ɑ���M��ł͂Ȃ��̂��H�A�Ƃ�����͖@�،o��ǂޔ\�͂���Ȃ��̂ł���B�܂��@�،o�̌㔼
6�i�ɂ͑S�āA�@�،o�Ƃ����P�ꈽ���́A�@�،o�ɂ����o�ꂵ�Ȃ����m���o�Ă���̂Ŗ@�،o�ł��鎖�͖��m�ł���B�܂��A������͊ԈႢ�Ȃ��U������̎v�z�I���W�̌`�Ղ������鎖������ʂ̌o�T�ł������Ƃ����͖̂@�،o���g��Ȃ��@�h���������K�Z�l�^�ł���Ƃ��������ǂݎ���B�����āA����I�ȏ؋���
���s�ӕ�F
�ł��� �B ���s�ӕ�F�͒��s(�U��)�ɂ�����(�C��)�ɂ��o�ꂷ��B
���s�ӕ�F�͖@�،o�̕�F�ł���B�����܂ł��Ȃ������ɓo�ꂷ�閳�s�ӕ�F�͖@�،o�N���Ȃ̂ŁA�ϐ�����F�̋N�����̂��@�،o�ł��鎖�͖����ł���B ���݂ɖ����ɂ�����
���s�ӕ�F�̐^���͕s�ځA�����͖��O�������邾���ƂȂ��Ă���B
| �����勻�P���A�@�،o���{����̍Z���B�����A�Y�i���@�،o�u�����v��� �����k�B���B�y����i��B�挫㔏o�B��荁i���j���s�B�]�i�╗�B���͐��́B ����F�F�@�،o���{���悭����Ɓu��k�B���i�v�Ɓu����i��v�͂��łɐ�l�ɂ���āA��(���@��Ɣ������Y���)�����ꗬ�ʂ��Ă����B�]�́A(��l��) �╗�����͔͂Ƃ���B |
�����̂悤�ɂ��̎���ɏo����Ă���������͐�s�o�T�ł͂Ȃ��@�،o���{���甲���o�����ʍs�{�ł��邱�Ƃ��킩��B
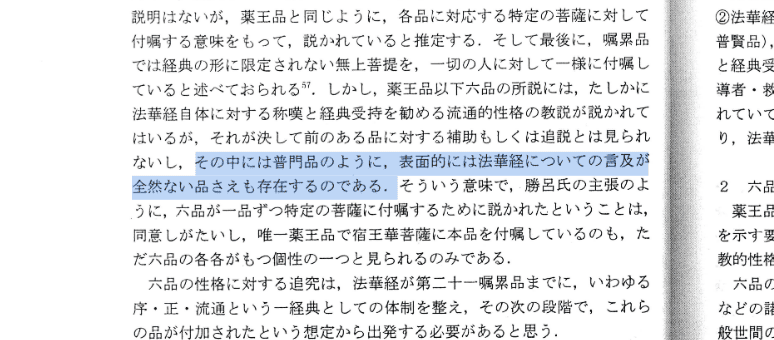
|
�������Y�i���@�@�،o�������� |
���u����i��v�́u�Y�i���@�@�،o�v����u���@�@�،o�v�ɑg�ݍ��܂ꂽ�B
������ł́A�u�Y�i���@�@�،o�v�Ƃ͂����Ȃ���̂Ȃ̂��H
|
�����u�勻�P���v�ҏW�F�u�Y�i���@�@�،o601�N�v�ɂ́A�{���ҁF���j�������s�ɂ��u�����v������B����ɂ��ƁA�����́u�勻�P���v�ɂ����āA��s�i�{���ҁj�́A���@��E�������Y��̊���ƁA�勻�P���̒�{�u�����V�t����̂́F����������t���ςɏ����ꂽ���́v������A��r�����Ƃ���A���@��E�������Y�̖@�،o�́A�勻�P���̒�{�ɂ���u����i����v���̑��������Ă����B����ŁA苓ߛ����E�B�������i��m�j�����͂��Ė��|����������|�A���ɏo�����Ƃ������Ƃł��B������̑��̔����Ă���i���lj�����܂����B��q���邪�A����i�d����͖k�����鎞�A�k�V���O���@苓ߛ����ɂ���āA�v�B�������ɂĖ|��Ă����B
���P�@�����̗t�@�L�t���L�����t�B�T���X�N���b�g��A�t�K����Ȃǒ����A�W�A�o�y�̌Â��o�T�̓��V�̗t�ɏ�����Ă���B
���Q�@�Y�i���@�@�،o���Z���g�i�͖��@�@�،o���������i��g���Ɂu�@�،o�@��vP287�Q�Ɓj ��1�A2������Ɩ�F�L�ώ��z�[���y�[�Whttps://www.kosaiji.org/hokke/hokekyo/translation.htm���p |
|
�������u������v�́A��{�ɂ����������� |
���̕��͓Y�i���@�@�،o�̏����ł���B
|
SAT�呠�o�e�L�X�g�f�[�^�x�[�X2018�FNo.264[Nos.262,263] |
�Y�i���@�@���S�����@�i�吳�V�����U�S9���@No.264 P134 b 24�s�j
���p�F�L�ώ�https://www.kosaiji.org/hokke/hokekyo/translation.htm
���������厱�@��B���W���V���B桐��@�B��`�L���B�X�����Y�B桖��@�@�B�l鄓�桁B����{�B�쎗�����V�t�B�Y���䢔V���B�]撿�S�U�B������{�B�������o���@�����B�䢑������@�B��t���L����B�Y���J�����R�B���쏊荎ҁB����i���B�Y��荎ҁB�Z���g�i�V���B�x��ߋy�@�t����i�V���B��k�B���i�B����i���B�Y���ښ��݁B���Z���V�O�B��{�ɗ���B���u����V��B���Ԉٓ��B���s�\�ɁB���k�B���B�y����i��B�挫㔏o�B��荗��s�B�]�i�╗�B���͐��́B���@�m�挳�N�h�єV�B�����j�������s�����B�����O�U����������@�t�B���勻�P���B�d���V�������t�{�B�x��ߋy�@�t����i�V���B���{�i��r�{�j�P�i�Ȃ��j荁i�����j �B�Z���g�i�X�v�����B��k�B���ʓ����i�B�ɗ��_�͔V��B���݊Ҍ����I�B
�́A�����̍��厱�@��A�W���̐��ɁA���@�i���@�،o�j��B��`�̛L���͍X�ɗ��Y�i�������Y�j�ɐ����āA���@�@��B�����l������ɁA��߂Ĉ�{�ɔB��i���@���j�͑����̗t�i���P�j�Ɏ�����B�Y�i�������Y��j�͋T䢂̕��Ɏ�����B�]�A�o���������Ĕ��i�ԁj���ɓ�{������ɁA�����͂��Ȃ킿���@�i���@�،o�j�ƕ���A�T䢂͂��Ȃ킿���@�i���@�@�،o�j�ƈ�i�܂��Ɓj�ɓ����B��i���@���j�̗t�͂Ȃ��₷�Ƃ��날��A�Y�i�������Y�j�̕��͂ނ��낻�̘R�Ȃ��B�����āA��i���@���j�Ɍ�����Ƃ���͕���i��Ȃ�B�Y�Ɍ�����Ƃ���́A�Z���g�i�̔��i���Q�j�A�x�O�߂���Җ@�t�ȂǓ�i�̏��߁A��k�B���i�A����i��Ȃ�B�Y�i�������Y��j�͂܂����݁i�i�j���ڂ��āA�i�i�j�̑O�ɂ���B��{�Ƃ��ɗ���i�i�j����тɕ���i�i�j�̌�ɒu���B���̊Ԃ̈ٓ��́A�����ċɂޔ\�킸�B�ނ��Ɍ���ɁA��k�B���i�i�j����ѕ���i��́A�挫�i�̖�j�̑��o���āA����₤�ė��s���B�]�A�╗���i���͂����i�̂��Ɓj��͂Ɛ����B���@�̐m�����N�A�h�т̍ɁA���j�������s��萿���A���ɎO�������i苓ߛ����j�E�����i�B�������j�̓�@�t�ƂƂ��ɁA�勻�P���ɉ����āA�d�˂ēV���̑����t�{�i���P�j�����i�Z���j���B�x�O�߂���і@�t�ȂǓ�i�̏��߂́A���{�ɂȂ������B�g�i�͍X�ɂ��̔����v���A��k�ᑽ�i�i�j�͓��i�i�i�j�ɒʓ����A�ɗ���i�i�j��_�́i�i�j�̌�Ɏ����A���݁i�i�j�����̏I���Ҍ����B
�@�،o�Ƌ�v�z�i���R�Y��j���m�w�p������38����2�� ���p
�y���k�B���B�y����i��B�挫㔏o�B��荗��s�B�]�i�╗�B���͐��́B�z
*�u��k�B���i�v�Ɓu����i�v�̘�������������ƁA��w�̌��҂��������o���āA�������������āA���ɍs���n�点���B���͂��̈╗�i���ӂ��j���i�����j���i�����j���ő��i�̂��Ɓj���ċK�͂Ƃ���B
������Ɩ�F�L�ώ��z�[���y�[�W���p
�y���k�B���B�y����i��B�挫㔏o�B��荗��s�B�]�i�╗�B���͐��́B�z
*�ނ��Ɍ���ɁA��k�B���i�i�j����ѕ���i��́A�挫�i�̖�j�̑��o���āA����₤�ė��s���B�]�A�╗���i���͂����i�̂��Ɓj��͂Ɛ����B
AI�|��
�y���k�B���B�y����i��B�挫㔏o�B��荗��s�B�]�i�╗�B���͐��́B�z
*��k�B���𖧂��Ɍ��āA����i����B�挫�͑����Č���A���_��₢�A���s�����B���͂��̈╗���i���A���͂�͂Ƃ����B
*��k�B���𓐂����B�y�ѕ���i�̘�B�挫�������ďo���B������������₢���s����B�]�͈╗���h���A���͂𐬂��Ĕ͂Ƃ���B
�@�B�|�� - AI�|��
https://www.machinetranslation.com/ja
Notes on translation:
1. � (steal/glimpse) �� �ނ��Ɍ��� (secretly/stealthily observed)
2. ��k�B�� (Devadatta) �� ���̂܂܉���
3. ����i�� �� ���̂܂܉���
4. �挫 �� ��l
5. ��� �� ��������Ƃ����₢
6. ���s �� ���z�����߂�
7. �i�� �� �i�� (�h�ӂ������ċ�����)
8. ���� �� �͂����͂��� (�K�͂��߂�)
���͉��L�̖|�������Ǝv���B������ɂ͉ߋ��`�������B
�y���k�B���B�y����i��B�挫㔏o�B��荗��s�B�]�i�╗�B���͐��́B�z
*�u��k�B���i�v�Ɓu����i��v��`���Ă݂�ƁA��l����(���@��E�������Y��)��₢���s���Ă����B�]�́A�i��l�́j�╗�����͔͂Ƃ���B
��l�̖|���s���Ă����B�Ƃ����̂́A�勻�P���ɂ������@�،o���{�����Č����Ă���̂ł����āA���_�A��k�B���i�Ɛ������@�،o�ł��鎖�͖����ł���B��q���邪�A�u�J���ߋ��^�v�ɂ��Ɖv�B������ �������イ��イ���A�ɂāA苓ߛ��������łɁA�|�Ă����B
�Y�i���@�@�،o�u���v
���{���2
�y�d�v�z�y���F���{��z�؎}���F�u�Y�i���@�@�،o���v8���ځF���m�w�p������38����2��
�Y�i���@�@�،o�u���v
���{���3
�y�d�v�z�y���F���{��z���R�Y��F���m�w�p����(1999) �ʊ�143��(38��2��) 088�u�@�،o�Ƌ�v�z�v�R����
���u�x�O�߁v�i�ܕS��q���L�i�攪�j����сu�@�t�v�i���@�،o�ł͖@�ҕi��\�j�ȂǓ�i�̏��߂́A
���{(���{)�ɂȂ������B���A�u��k�B���i�v�́A���@���̎������i��\��̌㔼�ł���B
���܂��A��i���@���j�Ɍ�����Ƃ���͕���i��Ȃ�B
�Y�Ɍ�����Ƃ���́A�Z���g�i�̔��i���Q�j�A�x�O�߂���Җ@�t�ȂǓ�i�̏��߁A��k�B���i�A����i��Ȃ�B
�Ƃ����͖̂@�،o���{�����Č����Ă���̂ł���B
�Ƃ������́A�u��k�B���i�v�Ɓu������v�͊��{�i���{�j�ɂ������ƌ������ł���B
�܂��A�������Y��́u�@�t�i�v�́A���@���� �� ���@�ҕi��\�̌㔼 �ł���B
�������Y�ɂȂ������Ă������ƌ����A�����炭���Y�|�̞��{�ɂ͖����������A�������Ă����B���̌�A
�C���h�̞��{�ɂ����āA�u����i����v�����L���ꂽ�Ƃ������ł���B
�����̐�����͖��炩�ɎU������̎v�z�I���W������A�U���������ꂽ���͖����ł���B
����ɖ��s�ӕ�F���o�ꂷ�鎖�͌���I�؋��ł���B���s�ӕ�F�͖@�،o�ɂ����o�ꂵ�Ȃ��@�،o�̕�F�ł���B
�u�ϐ�����F����i�ɂ��������������v
�������䐻�V��������i�S��������
�u�ϐ�����F����i�v�ɂ͈ȉ��̎]��i�����炭�c�邩��̌䐻�j���t���Ă��āA�@���ɏd�v������Ă��������킩��B
----AI�|��----
�ϐ�����F����i �]��
*******************
�L�`�@�O�U�@�t�@�������Y桁@���s
�@�k�@�V������@苓ߛ���桁@�d��
�w�䐻�V��������i�S���x
(�吳�V�����U�S9�� No.262 P198a 12�s)
�䐻�V��������i�S��
�V������F�B��ࡉޗ��S�B��̖����B���ݐ_�ʁB�V�@�E�B�����o���y�B���@�Z�x�B������B�O���@�C�B�}�L�����Bᢐ��ĐS�B㘝����i�B����ߎ���B���L�~��B���l�@�ӁB���@�@���S����i�ҁBਓx�E�ꜻ�V���F��B�l�\��Ȑ��S���V�B��O���G�B������ߏ����B�\�ň�؏���B�������s�v�c�B���ҁB�V�����摜�P�Ј��B�̘Ŏ��ʕ�B�g�lP�B���s��ਜ��B�v�V���n���B�F�R�lਁB�s������V���B��P�ғ����V���Bਜ��ґ��֒n���B�v���b�F�q�g�l��m���S���ŁB�̐_��芘�C�B�Ə�䟡�B���Ȑ��s�Ɖ������B���s�։����ԁB�v����V�k�B�ꉗਜ��B���ܗϔ@�Ǜ�B�D�Y�@�@�Z�ÁB�J?��?���B�s�Ԙœ��B�R�l���{�P�B��ਜ��ҁB�������V�B䑔\���S���B�C�Ȕ��B�z�ڔV�ԁB����P��BP�����P�l�B�̔V���ϔV��B�@�����y�o�B�g罏�А�B�����摜��ᶁB嫗L�ʕ�B�����{���B���P�O���B�ҋ����V�l�B�L�ߎ��s�m���B�T�ÐS���Ȏ����B���\�͐��S�B�g�P�njN�q�B�i���։��V�S�B�A�[���ʔV���BP�����B毗L�U涘��
�i�ً�N�܌������
���@�@���S�V������F����i�S
�L�`�@�O�U�@�t�@�������Y桁@���s
�@�k�@�V������@苓ߛ���桁@�d��
�ϐ�����F�Bࡉޗ��S�������āB�����̕ω��ɉ����B���݂Ȑ_�ʁB�@�E��Ղ��V�сB���o�̍��y�ɓ���B�@������A�~�ς���B����������B�O���͊C�̔@���B�����̂���҂́B����ȐS���B���������ď̂���B�����ɐ��ɉ�����B���ׂĂ̗~��́B�����@�ӂ�B���@�@�،o����i�ҁB��Y��E����^�̋����Ȃ�B�l�͏�ɂ��̌o���ς��B��O���G����B������߂̏��������邱�Ƃ��ł���B���ׂĂ̋��ł��邱�Ƃ��ł���B���̌����͎v�c�ɂ��āB���͎v���B�V���̕��͑P���摜���A����������B�̂ɕ��͉ʕ�������B�l��P�ɓ����B�����s�����Ƃ������Ă��Ȃ��悤�ɂ���B�V���ƒn���́B�F�l�̍s���ɂ��B�����̓��Ɉ�킸�B�̂ɑP�҂͓V���ɏ���B���҂͑����n���ɑ���B���b�F�q�g�l��m�̂��̐S�͑������Ȃ�B�̂ɐ_���͎�삵�B�Ə�͋��ɏ�������B����ɂ�萶�͌����ɔƂ����B���Ԃɑ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�����Ȏ҂́B��Ɉ����s���B�ܗς��̂ĂĝǛ�̔@���B�Y�@�݉z���ĊÂ����̂����ށB�J��H��?���B�������h�킸�B�������l���͖{���P�Ȃ�B�����ׂ��҂́B���ɋC���̕�ɉ߂��Ȃ��B�����S�����߁A�v����ς��B�C�Ȃ��A����������B�]�ڂ̊ԂɁB���͑P�ƂȂ邱�Ƃ��ł���B�P���ׂ��҂͑����P�l�Ȃ�B�̂̐ς�������́B����̓_�o�̔@���B�g罏�А�̔@���B���ł��A�摜�͐���ɐs����B�ʕ����Ă��B�ǂ��Ɉ��{���邩�B���͏�ɂ����O����B�B�����̐l���B�߂���m����߂��B�ÂĎ����Ɏ��邱�Ƃ��B���ɂ��̌o��\�͂��B�P�ǂȌN�q���B�i���։��̐S���������B���ʂ̕����L������B�P�̌����́B�ʂ����ĊU涘�����낤���B
���E�E�E�u�J���ߋ��^�v�u�@�ؓ`�L�v����v�B�������������イ��イ����
�_���F�㑺�^�����傤���F�u����i��̈�v�z�Ɋւ���l�@�v����
�㑺�^���搶�͑吳��w�����߂Ȃ����(�{���F���ω�)�ɖ��߁A�z�������ɗ͂𒍂��ł�ꂽ�悤�ł��B
�Ⴍ���ĖS���Ȃ�ꂽ�悤�ł��B�ނ��܂��A�ω���{���Ƃ��鎛�@�̑m���ł��������B
�_���̒��ŁA����i�ɂ��ďq�ׂ��Ă���܂��B
�㑺�搶�̘_�����ɂ���A�w�J���ߋ��^�x�́u���@�@�،o������\���i���邢�́A�����ɒ����v�̓��e�B�ł���B
1.�u�J�����^�v/���A [���U�ژ^] Vol. 55�@591(����)
�J���ߋ��^(�����N) 591
1...�@�؎O���S��ɖ@�@ �x�h�@�v���B�����גq��桚d�{
2...���ʋ`�S��ɖ@�@ �O���@�JꎓV������@�ܖ����ɖ��q�@桁@���桙_�@ 案��
3...�F�ܕ��ɗ��S��ɐ��ُo�@�؛����@�V����i�e�����@�m�S�^ �]�@�����^���@����S�@�������W�^�@ �E��ғ�
4...���@�@���S���ɓ�\���i������
�L�`�O�U�������Y桑��桏�l�S�\��ɓ��㍟���@�@���S��ܙɏ���k�B���i�Jꎕ��鎞�O���O�U�B����k�s�m������@�ى�������桑��S���{���@�ى������ґ��攪�ɏ�����i���d�u������鎞�k�V���O�U苓ߛ������v�B������桐`�{��荌�㔕ғ����攪�ɒ��Z����F�����Z��哂�O�U�����d桍݉��`�����s�ʏo���@���S�\�Ɉ��]�������@�؈����Ɉ�㐼�W�O�U���@��桑�O桖��@�@���S���ɓ�\���i�������@�V���O�U����������@�t�Y�i�o�S�O���y���T�^���E�O�S���{��桑��Y�i�����]���@��|���@�Y桞�鄓�{���F�L荌쏊荎ҕ���i���Y��荎��Z���g�i�V���x��ߋy�@�t����i�V����k�B���i����i���Y�ښ��ݍ��Z���V�O��{�ɗ�����u����V�㑴�Ԉٓ����s�\�����k�B���i�y����i��挫㔏o��荗��s�]�i�╗���͐��͑��@�m�挳�N�h�єV�Έ����j�������s������������������@�t���勻�P���d���V�������t�{�x��ߋy�@�t����i�V���z�{�P��Z���g�i�X�v������k�B���ʓ����i�ɗ��_�͔V�㚖�݊Ҍ����I���卷�ꐜ�������W�L��q�K�܋^�f�����Y�i�`���Z桎O�ݎO�
�y��́z
1...�@�؎O���S���
�@�@ �x�h�@�v���B�@����@�גq���@桁i��j�d�{�i�P�Ɩ{�j
2...���ʋ`�S�i���ʋ`�o�j�@���
�@�@ �O���@�JꎓV���@����@�ܖ����ɖ��q�i�ǂ�܂����₵��j�@桁i��j�@���桁@�_�@桁@���(������)
3...�F�ܕ��ɗ��S�i��k�B���i�j�@���
���i����́j�@�ُo�i�ٖ�j�@�@�؛����i���i��\��j
�V����i�e�����@�m�S�^�i�o�O���L�W�j�]�����^��
����S
���@���@���W�^�@ �E��ғ�
4...���@�@���S���ɓ�\���i���i���邢�́j����
�y�����z
3...�F�ܕ��ɗ��o�i�@�،o�̉��ʁF��������܂Ղ�[���F���ǂ�ӂ肫�傤�F��k�B���i�̂�)���i��\��̕ʍs�{
�i����o�F���₭���傤�^����o�F����҂̖����s���Ȍo�T�̂��Ɓj
�ȏ�11��
�L�`�i�悤����/��`�j�O�U�@�������Y�(��)�@����(��)�@��l�S�i���1�`4�́j�@�\��Ɂ@����i1�Z�b�g�j�@���i���̒��́j�@���@�@���S��ܙɁ@��(�n�߂�)�@��k�B���i�@�Jꎁi���傤����/��)�@���鎞�@�O���O�U(�O���̎O��)�@�B�����(����܂ڂ���)�@��(�ƂƂ���)�@�k�s�悤�Ƒm��(�������傤)�@����(�������/�m��)�@�@��(�ق�����)�@��(�ɂ�����)�@������(������/�����̎�)�@�(��)�@��(����)�@�S(���o��)�@���{�@�� (�����)�@�@��(�ق�����)�@��(�ɂ�����)�@��? �i�z�[�^�������j���ҁ@��(����)�@�攪�Ɂ@��(�n�߂�)�@����i���@�d�u��@�����鎞�@�k�V���O�U�@苓ߛ����@��(�ɂ�����)�@�v�B�������(��)�@�`�{(�L�`�悤����/��`�̖{/�������Y��@�،o)�@���(����̌��ɂ�)�@��(�̂�)�Ɂ@�(������)�@�ғ��@��(�܂�)�@�攪�ɒ��@�Z����F���@��i�ɗ���_��j�Z��@�� ���@�O�U�����@�d�(�d��)�@��(����)�@���`(���ƈӖ�)���@��(�����)�@�s(�ł͂Ȃ�)�@�ʏo(�P�Əo�ŕ�)
�y��z
�L�`�i�悤����/��`�j�̎O�U�@�t�A�������Y�(��)�@����(��)�@��l�S�i���1�`4�̂��o�\��Ɂj�́A����{�i���F1�Z�b�g�j�ł���B���̒��̖��@�@���S��ܙɎn�߂̒�k�B���i���Jꎁi���傤����/��)���鎞�ɊO���̎O�U�@�t�A�B�����܂ڂ����ƂƂ��ɗk�s�̑m��(�m�̈�)����(�m��)�ł���@��(�ق�����)�ɂ����Ċ�����(������/�����̎�)�ɂĖ|�ꂽ�B���̂��o�̞��{�͖@�فi�ق�����F�m���j�ɂ���Ę�?�i�z�[�^�������j���盒�҂����B���̑攪���n�߂̕���i�d����͖k�����鎞�A�k�V���O���@苓ߛ����ɂ���āA�v�B�������ɂĖ|�ꂽ�B�L�`(�悤����/��`)�̖{(�������Y��@�،o) �̌����Ă������ɂ��A��(�̂�)�ɑ����ĕғ������B�܂��A�攪���̖�F���̎�i�ɗ���_��j�Z��́A���̌����O���̏d��(�|��̖|��)����A����͒P�Əo�ŕ��ł͂Ȃ��B
�ȏ�
���@��E�������Y�Ȍ�ɁA�C���h�ɂ����đ��L���ꂽ�@�،o���{����̖|��ł���ƌ��������킩��B
���@���S�\�Ɂ@���i���邢�́j�@�]�����@���@�@���@���Ɂ@���i���F1�Z�b�g�j�@���W�O�U�@���@��桁@��O桁i��j
���@�@���S���ɓ�\���i�����Ɂ@�@�V���@�O�U�i�O���@�t�j
���������@��@�t�@
�Y�i�o�S�O���i�Y�i���@�@�،o�����j
�y�с@���T�^�i�ȉ��ȗ�)
���E�O�S���{��桑��Y�i�����]���@��|���@�Y桞�鄓�{���F�L荌쏊荎ҕ���i���Y��荎��Z���g�i�V���x��ߋy�@�t����i�V����k�B���i����i���Y�ښ��ݍ��Z���V�O��{�ɗ�����u����V�㑴�Ԉٓ����s�\�����k�B���i�y����i��挫㔏o��荗��s�]�i�╗���͐��͑��@�m�挳�N�h�єV�Έ����j�������s������������������@�t���勻�P�V�������t�{�x��ߋy�@�t����i�V���z�{�P��Z���g�i�X�v������k�B���ʓ����i�ɗ��_�͔V�㚖�݊Ҍ����I���卷 �ꐜ�������W�L��q�K�܋^�f�����Y�i�`���Z桎O�ݎO�
�i1�`4�j���v11���@�@��i�{�̔�/����/1�Z�b�g�j
���u��k�B���i�v�Ɓu������v�������@�،o���{����̖|��ł��邱�Ƃ��킩��B
��k�B���i�̏��l�����͔������Y�Ȍ�̞��{�i��{�j�ɂ����Č������Ă����ƌ������ł���B
�Ȃ��Ȃ�u���@�،o�@27�i�@���@���@286�N�@���i�@�吳��263�v�ɂ͂��邩��ł���B
2.�u�J�����^�v/���A [���U�ژ^] Vol. 55�@545(����)
�J���ߋ��^(�����N)
545
����@���q�����i�₵�Ⴍ�����j �B�@�����i�U(������)�B�@�D�k��(������)�l�B�@�������{(�Ƃ��Ɋw��)�@苓ߛ����B�@
��(�ɂ�����)�@���鎞�@�(����)�@��冡��(����i�k���j�̍ɑ�)�F����(�F���삤�Ԃ�) �@���i�ɂ����āj �l�V�����@�y�i�y�сj�@�d�����B�@桁i��j�@�������S�@���@�O������S�@�����@���@�L�@��_���J�S�@���
���i�܂��j�@�]�i�U���@桁i��j�@���ȁi���܂��Ɂj�@���S�i���̌o�j�@����(���ꂷ�Ȃ킿)�@�o�O(���|��)�@苓ߖ��q�i����Ȃ₵��j�@���o�V�ҁi������҂Ɓj�@�s���i��v���Ȃ��j�@�ʏ�(�ʂɏグ��)�@��|�i�Q�����j�@�䑶�ҁi�����ҁj�@��i�s���j
��(�ق�)
���@�@���S�@����i�d�u��@��Ɂ@�݉v�B�������@桁@���@�ғ��@�攪�Ɂ@����i
���趎��S�@��Ɂ@���i���邢�́j�@���S�����`��\�O��@�݁@�v�B������� �i��j
�Ō��S�@��ɑ��o�o�@��鰁i�k鰂ق����A386�N - 534�N�j�@��x�i��u�i�ڂ����邵�j�ڂ����邵�E�|��ҁj�(��)�ғ��{�@�݉v�B������桁i��j
���F��l���S�@��Ɂ@ ���i�ɂ����āj�@�����@�p��l�V����桁i��j
�J�g�M��@��(����ɂ�)�@�����[�^�@ �E�l���ܙɁ@�O��Ɂ@���݁i�����j�@��i���Ƃ́j�@�O�Ɂ@荁i���j�{
����@苓ߛ����i����Ȃ������j�B�@�����u���B�@�k��x(�k�C���h)�@?ɒB(�K���_�[��)���l�B�t�k���V�ҒB䢋��B�@��(������)�@���鎞�@���i�ɂ����āj�@�l�V�����B桁i��j�@���F��l���S�B
��i���̌�j
�@
�(�@)�@譙(�@�̍�(�S�i���傤-����j�́A�����ɂ��đ��݂����S)�@��(��) �@�F���L�@( �F���L���Ԃ�i551�N�\578�N2��27���j)��(�̌��)�@�v�B(�������イ)�B���i�ɂ����āj�@������(��イ����)�@��桁i�Ăі|��j�@�����@���@�O���B�@����(����Ȃ�����)�@���(�@�ɓ���)�@�X(�����)�@�A�|�(�L���|��)�B
���@��q�i��q�j ���ڍׂ͏�L�u�J�����^�v/���A���U�ژ^ Vol. 55�@591�Q��
�J���ߋ��^
������������傤�낭
Kai-yuan shi-jiao-lu �����A���̒q���҂̖�o�ژ^�B�����āw�J���^�x�B 20���B�J�� 18 (730) �N�����B
�����ɕ������`����Ă��炾������660�N�Ԃ�176�l�̐l�X�ɂ���Ė�o���ꂽ�A
�召��̌o���_�̎O���Ɩ�o�҂�̓`�L�A���� (��ҕs���̂���) �A���{�Ȃǂ��L�^���������B
�S���� 1076�� 5048�������߁A���R�Ƃ��āA�L�������m�ł��邩��A
�Ȍ�̑呠�o�̓��e���K�肷��W���ƂȂ����B
�o�T�@�u���^�j�J���ۑ�S�Ȏ��T �����ڎ��T�u���^�j�J���ۑ�S�Ȏ��T �����ڎ��T�ɂ��ā@���
���E�E�E
�_���F�㑺���傤���F����i��̈�v�z�Ɋւ���l�@
�_���F�㑺���傤���F����i��̈�v�z�Ɋւ���l�@
�������f�^�����B���������Ă���̂��킩��Ȃ��B
�u�Y�i�@�،o�v�́u�����v�ɂ��ꂼ��Ɨ��̘���Ƃ��ďЉ��Ă���B
�Ƃ��邪�A����Ȏ��͏�����Ă��Ȃ��A�|��҂��Ⴄ�����ł���B
�@�،o���甲���o�����ʍs�{�ł���B
�u�Y�i���@�@�،o�̏����v�ɂ���Ȏ��͏�����Ă��Ȃ��B
�勻�P���ɂ͒�{������A��r�������ʁA���@��┵�����Y�ɐ��������Ă���Ə����̍�҂͌����Ă���B
�����
��L�́��u�J�����^�v/���A���U�ژ^ Vol. 55�@591�ł́A
���@�@���S���� �@�فi�ق�����F�m���j���A��闐�i�z�[�^�������j���盒�҂������{�ł���B�Ɩ��L����Ă���B
���E�E�E
����i���یo���ׂ̓Y���ɂ���
�� �� �� ��
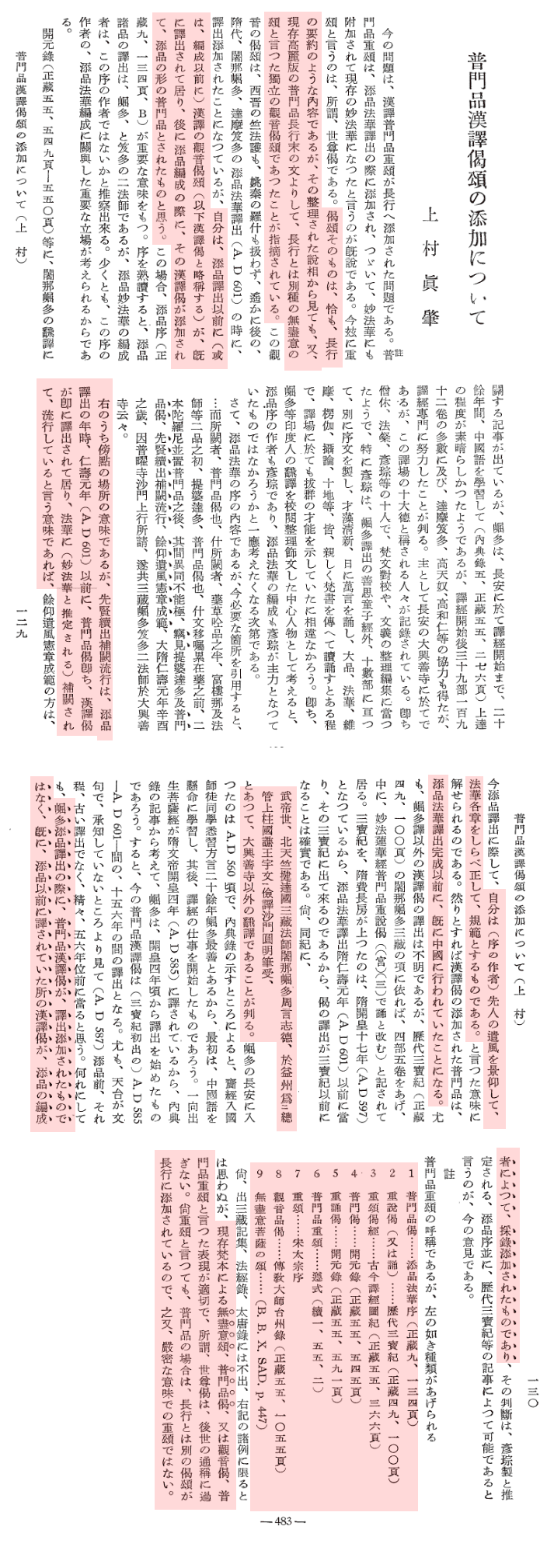
��̕�����ˁ`�������Ă�ˁ`��
���s�ӕ�F�͒��s(�U��)�ɂ�����(�C��)�ɂ��o�ꂷ��B ���s�ӕ�F�͖@�،o�ɂ����o�ꂵ�Ȃ��B
���s�ӕ�F�͖@�،o�̕�F�ł���B����i����́u�d��v�ł���B
���łɓY�i�ȑO�ɖ�Ă��������́A�@�،o���甲���o�����ʍs�{�ł���B
�u�Y�i�̕Ґ��҂ɂ���āA�̘^�Y�����ꂽ���̂ł���E�E�E�v
����i����́A�勻�P�����{����̕Ґ��ł���B
�u����i�̏ꍇ�́A���s�Ƃ͕ʂ̘����s�ɓY������Ă���̂ŁE�E�E�v
�Ӗ���������ʁB
���O���I (�ɑ�\�O�嘩�^���U��) in Vol. 49 �����N
�� ���O��L�́u�o�\�v�Ƃ��ĔF�߂��Ă��Ȃ��B
����L�̂P�@4�@5�́A����i�́A�����̞��{�@�،o����|��ʍs�����{�ł���B
2�@3�@6�@7�@8�@9�@�͌������Ȃ��̂ŁA�ƍ��ł��Ȃ��B
���Ȃ킿���̌o�T��������Ȃ��B
����i�͏d��ł���B
����
�i����l���j���Y�҂����̎�ɗ����A���܂ɂ����Y����悤�Ƃ��Ă����
���Ă��A�i���̐l���j�ώ��݂�O���Ă���ƁA���̂Ƃ����͂��Ȃ��ȂɂȂ�B
����u��������� �ՌY�~��I �O���V���� ���q�i�i�Ӂv
�U��
�������Y����悤�Ƃ��Ă���҂������A�ώ��ݕ�F�E��m��吺�ŌĂԂ�
��A���Y�l�����̓��͂��Ȃ��Ȃɍӂ���ł��낤�B
����u�ᕜ�L�l���c��Q�C�i�V������F���ҁC�ޏ�������q�i�i�ӁC������脫�B�v
���E�E�E
�_���F�㑺���傤���F����i��̈�v�z�Ɋւ���l�@
�㑺�^�����̘_�����A
����Ȃ��ƒ��ׂĂǂ��Ȃ�̂��H�������n�ł��������̂��H
���̕ӂ����E���낤�B
���E�E�E
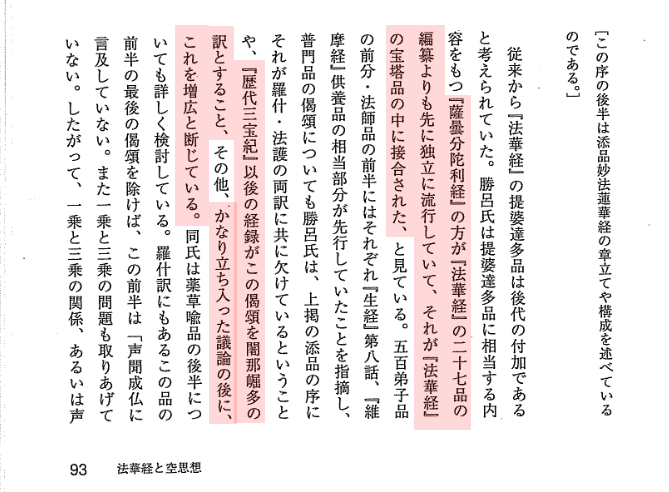
���R �Y��i������� �䂤�����A1925�N1��2�� - 2004�N3��29���j�́A���{�̕����w�� �B�w�ʂ́A���w���m�B ���s��w���_�����B
���Ȃ藧���������c�_�̌�ɂ���L�ƒf���Ă���B
�ƌ����Ă��邪�E�E�E
����i����̑��L������Ƃ���A�C���h�ɂ����镁��i�U������̐i�����W�ł���B
���E�E�E
�u�ω���F�ƕ���i�v�O�F���e���m�_�����B
�u�@�ؓ`�L�v�ق����ł�(�W���I�F��ҕs��)
�y�����E����̑m�ː�B�@�،o �̓`��A�@�،o���u�߂������m�̓`�L�A�@�،o���_���E���h�Ȃǂ��L�q�������z
����
2 �����@�،o�Ɗω��o
�������Y�͒��x������1600�N�O��406�N�Ɂw���@�@�،o�v���������A���m�̂悤�ɁA��
���ɂ́u�ϐ�����F����i�v�̋��Е������������Ă��Ē��s�̕�������������Ă����B
���Ȃ킿���݉�X�����Y��Ə̂��Ē��s�Ƌ��Ђ܂œǐ����Ă�����̂́A�t�ߖx�����Z������
�u�Y�i���@�@�،o�v�ɂ����̂ł���B���́u�ϐ�����F����i�v�͐l�X�̋~�ς�������̂�
���čD�܂�A��������u�@�،o�v�Ƃ͕ʂɐ��ɗ��z���Ă����B
����ȑO�Ɋ��ɖk���ł́A
�ܖ������@�t �i�ɔg�ӕ�F�j���ʍs�{�Ƃ��ė��z���Ă���
�i�u�ω����`�v�吳��34�A891c�j�A�܂��ʖ��u�c�r���o�v�Ƃ��Ă�Ă���
�i�u�@�ؕ���v�吳��34�C144c�j�B�܂��A��L�̎]�Ђ�����킩��悤�ɁA
�u�ϐ�����F����i�o�v�Ƃ��Ă�Ă����悤�ł���B
�܂��A�u�@�ؓ`�L�v�iT51�C52�Db�j�ɂ́A
�������o��J�B ���W�i��N���@���(��)�B
����i�o�ꊪ�B���W�㍹��_������(��)�B
�ϐ����o�ꊪ�B��`���Y��������ꡉ��ځB
�ϐ����o�ꊪ�B�v����z���߉��������B
����d����(��)�ꊪ�B�������k�V�����Ś�����@�œߖx���B�݉v�B���B�����N�H�F���ځB
�ߏ�܌o�B�啔������i���{�B���L����i�o�ꊪ�\���B�ޑ囉�ϕ���{�B��@�ؕʏo�B
�Ƃ����āA���Y�Ȃǂ̎O�{�����킹��
�ܖ{�̊ω��o�����Ԃɗ��z���Ă������Ƃ��킩��B�܂��A���ڂł���Ƃ��邪�A�u�����ϐ����o�v�iT51�C 52c�j���������悤�ł���B
�ߏ�܌o�B�啔������i���{�B���L����i�o�ꊪ�\���B�ޑ囉�ϕ���{�B��@�ؕʏo�B
��
�ȏ� �܌o�B ������������i(�@�،o)�Ɠ��e�����B���łɂ���A����i�o�ꊪ�\���B
���̑��ϕ����(���όo�����ق����Ⴍ���傤�F����t�������)�Ɠ��{�B�@�،o�ł͂Ȃ��ʖ{�B
���
��L�܌o�́A�@�،o����i�Ɠ��{�ł���B
�O�F���e���m�́A�u��������u�@�،o�v�Ƃ͕ʂɐ��ɗ��z���Ă����v
�ƌ����Ă��邪�A�������Y��̒�{�̌�̎���ɃC���h�ɂ����āA����i�ɘ��lj�����A
���ꂪ�@�،o�Ƃ��ē`���A�ʍs�{(�傫�Ȍo�T���甲���o���Ďg����{)�Ƃ��āA�o����Ă����Ƃ����Ӗ��ł���B
�ܖ������@�t �i�ɔg�ӕ�F�j�́A����i�Ɠ��{�ł͂Ȃ��B
�u�@�ؓ`�L�v���W���I�A��ҕs���ł���B�������Ȃ���A����i�����{�@�،o����̖|��ł��鎖���ؖ����Ă���B
���E�E�E
���h���Îu(������w)�@�s�@�،o�t�������u���ɂȂ鋳���v�̃��l�T���X����
�����Ɨ����ė��s���Ă������̂��A�l�ܐ��I�ɂȂ��Ė@�،o�ɑg�ݍ��܂ꂽ���̂ł���B
�ƌ����Ă��邪
�ȉ��ϐ�����F����i�̈ꕔ
���s�ӕ�F�͎ߑ��Ɍ������B�u������A�킽���͍����̊ϐ�����F�ɋ��{���܂��v�����Ė��s�ӂ́A����S����̉��̂��邻���ĕ��̏�������ƁA�����^���Č������B�u��F��A���̕����ǂ������Ƃ肭�������v���̂Ƃ��ϐ�����F�͂�����Ƃ�Ȃ������B���s�ӂ͍Ăь������B�u�ǂ����A��������ނƎv���āA���̕������Ƃ肭�������v���̂Ƃ��ߑ��͊ϐ�����F�Ɍ������B�u�ϐ�����A�܂��ɂ��̖��s�ӕ�F�ƓV�̂��̂Ɛl�Ɣ�l�Ə��X�̉�O�����ނ��䂦�ɁA���̕�����ׂ��ł���v�ϐ�����F�͉�O�����݁A�����ē��A��͎߉ޖ��ɕ��A��͑��̓��ɕ�[�����B
���̂悤�ɕ���i�ɂ́A����@�����o�ꂵ�Ă���A�@�،o�ł��鎖�͖����ł���B
������
�u�ϐ�����F�͉�O�����݁A�����ē��A��͎߉ޖ��ɕ��A��͑��̓��ɕ�[�����v
�Ƃ����͖̂@�،o�ɑ���A�˂ł���B
������͊ԈႢ�Ȃ��U������̎v�z�I���W�̌`�Ղ������鎖������A����i�U�������ɃC���h�ł���ꂽ���̂ł���B
����I�ȏ؋��� ���s�ӕ�F �ł��� �B
���s�ӕ�F�͒��s(�U��)�ɂ�����(�C��)�ɂ��o�ꂷ��B ���s�ӕ�F�͖@�،o�̕�F�ł���B
���E�E�E
�y�������C�F�_���F��ɗ��Ɗω�����z
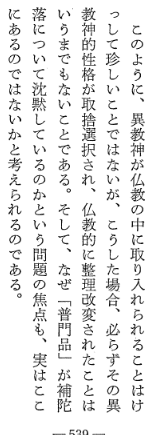
����i���Ȃ���ɗ��ɂ��āA���ق��Ă���̂��H
�ƌ����Ă��邪�A
��ɗ��Ƃ����v�z�́A�،��o�̓��@�E�i����̐����ł���B
�@�،o�̎���ɂ͖����v�z�ł���B